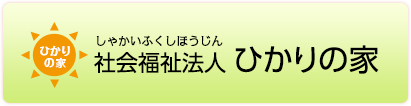ひかりの家のとりくみ
「誰もが安心して暮らせる地域社会を目指して」
1973年、任意団体「刈谷地区心身障害児者を守る会」によって、障がいのある子もない子も共に育ち合う場として「ひかりの家」が誕生しました。すべての子どもたちを分け隔てなく受け入れる保育を大切にし、地域に根ざした活動を続けてきました。
しかし、医療的ケアが必要な重度の障がいのある子どもたちへの支援の必要性が高まる中、より専門的で安定した運営体制が求められるようになりました。職員の労働環境の改善も視野に入れ、2002年(平成14年)に「社会福祉法人ひかりの家」として法人化し、福祉事業の実施主体を引き継ぎました。
法人化以降、子どもから大人まで、人生のさまざまなステージを支える多彩な事業を展開しています。
| 2006年(平成18年) |
全国的にも珍しい、重症心身障がいの方々を主な対象とした「ひかりワークス風鈴(生活介護・短期入所)」を開所。 |
| 2010年(平成22年) |
障がいのある子どもと家庭を支える「子どもと福祉の相談センターひかりのかけ橋」を開設。 |
| 2012年(平成24年) |
「ひかりライフ風花(グループホーム・短期入所)」および、居宅介護事業所「ひかりサポートかざぐるま」を開設。「ひかりっこ」は児童発達支援センターへと種別変更し、「保育所等訪問支援」や「一時保育事業」など、地域での支援を広げました。 |
| 2015年(平成27年) |
学齢期の子どもたちの放課後の居場所として「放課後等デイサービスひかりきらきら刈谷」を開所。 |
| 2017年(平成29年) |
「ひかりライフそよ風(グループホーム・短期入所)」を開所し、地域での暮らしを支える体制を拡充。 |
| 2020年(令和2年) |
「ひかりワークス鈴の音(生活介護)」を開所。 |
| 2021年(令和3年) |
法人本部を「ひかりワークス風鈴」へ移転。 |
| 2022年(令和4年) |
創立20周年記念式典を開催。 |
| 2023年(令和5年) |
新たに「ひかりの春風訪問看護ステーション」を熊野町に開所し、医療的ケアを含む在宅支援の充実を図りました。 |
これらの事業はすべて、「誰もが安心して暮らせる地域社会をつくる」という法人の理念に基づくとともに、「ほいやるぞん」の魂を受け継いでおります。
そして今もなお、「ひかりの家」の原点である「仲間とともに支え合いながら、誰もが住みよいまちづくり」の実現に向けた歩みを、守る会と共に積み重ねています。
ひかりの家がうまれるまで
始まりのとき、めざしてきたもの
1965(昭和40)年9月25日、「刈谷市心身障害児(者)を守る会」(以下、守る会)の設立総会が刈谷市の会議室で開かれました。設立目的として掲げられたのは、「重度の心身障害者」のための「施設」を地域につくること、そのために、300万円の資金を5年を目途に集め、施設の公的な運営を市に働きかけていく、というものでした。
発足時の会員数は役員も含めて16人。民生委員や保健師(当時保健婦)、保健所の医師たちが中心でした。障がいのある子どもたちの親の会も地域ですでに発足していましたが、守る会は、「当事者」ではない人たちが声をあげて、立ち上げました。
刈谷市の隣の東浦町にある愛光園の創立者で、発足時から会を見守ってきた皿井寿子さんは、守る会の10周年誌に次のように書いています。
〈守る会のあり方がすばらしいと思うのは、この会の目的が会員の権利を守ろうとすることではなく、伊藤さんが障がい児を知ってやむにやまれぬ思いで動き出し、子どもたちを守ろうという輪をひろげていったことです。その動きが地域の中に浸透していったのは、久米先生をはじめ会の中心になられた方々の大きな努力があったからだと思います〉
ここに登場する「伊藤さん」とは、刈谷で当時保健婦をしていた伊藤寿美ゑさんにほかなりません。「久米先生」は、守る会の初代会長久米正枝さんのことです。自宅で学習塾を開くかたわら、民生委員として福祉にも心を配っていました。
最初の歩み~Y君との出会い
寿美ゑさんは、母親としての子育てが一段落したころ、保健師になろうと学校に通い出しました。30代半ば近くになっていました。卒業して最初の赴任先が刈谷保健所(現衣浦東部保健所)でした。守る会発足の5年ほど前、未熟児として届け出のあったY君の家を初めて訪問します。
寿美ゑさんの手記によれば、2500グラムで生まれたその男の子は、生後1カ月近くたっても、「片方の目はつぶれ、反対側の眼は眼球が小さく目やにがいっぱいくっついていた」といいます。発育は悪く、笑うこともしない、赤ちゃんらしい声も出ません。母親の言葉が、寿美ゑさんの胸に突き刺さりました。「生まれてこない方がよかった」寿美ゑさんはY君宅への訪問を重ねます。1年たっても、Y君は、はうことも歩くことも、しゃべることもできず、目も見えないままだったといいます。施設での療育が必要だと考えた寿美ゑさんは、重度障がい児の施設を探し求めました。開園したばかりの「びわこ学園」(滋賀県大津市)へ、幼いY君をおぶって、おむつと哺乳瓶を持って寿美ゑさんは訪ねていきました。「まさか、あなたが子どもをおぶって来るとは思っていなかった。わたしは子どもを見ると弱いんだ」。びわこ学園の岡崎英彦園長(当時)にそう言われたそうです。保健師の仕事としてではなく、個人として止むにやまれぬ気持ちからの行動だったに違いありません。懇願の末、入園が実現します。守る会設立の前年、1964(
昭和39)年春のことでした。
当時、刈谷市教育委員会の社会教育課の職員で、85歳になる野村正直さんは、半世紀前を振り返って次のような手記を寄せてくださいました。
〈Y君とのはじめてのドライブ。「ほい野村さん、次の日曜日Y君を近江学園に連れて行くで、自動車出しておくれん」「近江学園ってどこにあるんだ」「三井寺の隣あたりだよ…それまでに、よう聞いとくからね」。当日の朝、寿美ゑさんを刈谷市駅に迎え、Y君の家に行く。「あそこんち、百姓に行くときは、Y君が外に出ないように柱にくくっとくんだわ、ちょっと可哀そうじゃんね」当時はまだ東名高速道路がなく、国道1号線で四日市、亀山から鈴鹿峠を越えなければならなかった。途中の茶店で冷たいジュースを買い、ひたすら栗東へと向かった。三井寺は大津市内にあり、この寿美ゑさん説明の難コースを克服して、どうやら到着することができたのでした。〉
野村さんも、心意気に感じて個人の立場で協力していました。当時を知る人によれば、柱にくくりつけたと言っても、縛り付けたわけではなく、高い縁側から落ちないように、体をひもで結んであったということのようです。農業で両親とも家をあけるので、そうするしかなかったようです。「障がいのある子たちのために、民生委員の人やボランティアの人たち、みなさんが必死で頑張ろうとしていましたよ。子どものために真剣でした」と野村さんは言います。
話しは少し先へ飛びます。それから20年くらいたった時に書いた文章のなかで寿美ゑさんは、Y君を「びわこ学園」に入れたことを振り返っています。「果たして当時私のしたことがよかったのだろうか」と、親元から離させてしまったことを悔いているのです。「Y君のため」を思って夢中で療育の場を探し求めたはずでした。けれども、その行為自体の是非を改めて省みると、苦い思い出としてかみしめざるを得なかったようです。
自分自身のそうした心境の変化について、「自らが住む地域にある施設へ親も一緒に通い、共に育ち合って行くことが望ましいと考えるまでに私自身が成長してきた」からだと書いています。「親も一緒に通い、共に育ち合って行く」。そんな願いに応えることのできる場所のひとつが、やがて形になっていく「ひかりの家」にほかなりませんでした。
「200円貯金」の呼びかけ
Y君のために心を砕いていた寿美ゑさんは、一緒に動きだしていた仲間たちと、施設づくりを考え始めました。家の中だけで日々を過ごすことを余儀なくされている重度の障がい児はY君だけではありません。守る会の記録によれば、国会議員や有名人、地元の有力者にも理解を求める手紙を書き続けたといいます。友人や知人、職場の同僚らにも訴えました。同じ保健所所属の医師安田純子さんとは特に何度も話し合いを重ねました。
「専門の施設に入れてあげたい」「施設をつくるのに1千万円はほしい。いや、2
、3百万円でもいい」。資金集めのために、だれにもできることから始めよう。考え出されたのが、「毎月200円ずつ出し合っていく」という「200円貯金」のアイデアでした。実行に移されたのは1962(昭和37)年の11月ごろ、守る会設立の3年ほど前でした。「ほい!子どもたちのために何かしてあげりん。200円出しん」寿美ゑさんは、そんなふうな三河弁で身近な人に呼びかけ始めました。間もなくして、刈谷市役所民生課の神谷龍介福祉主事の橋渡しで、のちに守る会の初代会長になる久米さんとも出会います。10周年誌には、二人の出会いのことを久米さんがユーモアまじりに書いた文章が引用されています。
〈市役所の福祉主事が「熱心な保健婦がいるからそのうち訪ねていくよ」ということで初対面となったわけです。パリッとしたやり手の人のことを想像していたら、この人のどこに情熱を秘めているのかと思うほど平凡なおばさんタイプ。これは向こうも同じで、恐る恐るドアをあけたら、わたしをお手伝いさんかと思ったとは、後日わかったことです。四重苦の男児(Y君)を訪問で発見したが、個人の力ではどうしてあげることもできない。この子以外にも、きっと重障児(原文のまま)はいるに違いないから、心ある人に働きかけてお金を寄せ合い、検診に連れていくとか、日用品に贈るというような活動をまずしようというのだ。月額200円ということで、早速仲間に入ることにしました〉
「200円貯金」の輪が次第に広がり、守る会設立の母体になっていきます。
設立当時の社会のまなざし
守る会が設立された当時、障がいのある子どもたちはどういう環境のなかに置かれていたのでしょうか。
設立前年の1964年は新幹線が開業し、東京オリンピックが開かれました。刈谷保健所が、刈谷、知立、碧南、高浜に住む重症心身障がい児の実態を調べました。その年の11月に東京で開かれた全国肢体不自由児の療育研究会で発表するためです。就学免除、就学猶予の届け出のあった
家を保健師が訪問しました。
寿美ゑさんは、手記のなかで、当時の訪問で出会った子どもたちの様子を伝えています。50年記念誌第5章の扉に一部引用しました。障がいのある子に対する、当時の世の中の人たちのまなざしも垣間見えます。
〈届け出に栄養失調と書いてあり、不審に思いながら訪ねてみれば、ダウン症児が広い庭で一人砂いじりをして遊んでいました。声をかけると、ニッコリ笑ったその顔は仏様のようで今も忘れられません。
8歳になった男の子は就学免除でした。この子は動きがはげしく、家族のすきをみてすぐ家を飛び出し、ある時は電車を止めてしまったこともありました。米2俵入りの貯蔵缶の中に落ち込み、引っ張り上げるのに何時間もかかったり、鼻の穴にゴム管を突っ込んであわてて病院に走ったりと、家族は気持ちの休まることがありませんでした。やむを得ずに柱にしばりつけておいたのに、退屈のあまり足の指先で畳表に穴を何か所もあけてしまったそうです。
ぴょんぴょんと飛び上がってじっとしていられない5
歳の女の子を乳母車の中に入れ家の前で遊ばせていたのですが、通りがかりの若者がその女の子を見ると、「やいやい、おかしなものがいるぞ」といって、わざわざ車をバックさせてのぞいてみて走り去るということがあり、家族は耐えられなかったといいます。
ある家の奥の暗い物置をのぞいて、しばらく経って中の様子が見えてくると片隅の箱の中に子どもが一人いました。家族から「ほうっておいてほしい、いらんことはせんでくれ」といわれたことも何度かありました。〉
守る会の設立時の趣意書は、その書きだしで、作家の水上勉氏が月刊誌「中央公論」に載せた文章についても触れています。1963
(昭和38)年6月号に載ったその記事は「拝啓
池田総理大臣殿」と題されていました。「脊椎破裂」と診断され、医師や看護師から見放されたような子どものことを赤裸々につづりながら、重症心身障がい児のための公的な療育施設の拡充を社会に切々と訴える内容でした。
設立趣意書は、この水上論文のほかに、当時起きた、脳性まひの子を持つ親が、子の将来を案じた挙句に手にかけてしまった事件にも言及しています。「こうした家庭の苦しみや、悩みを少しでも解決していく方法はないものか。障がい児に対して生きている幸せを与えていくことはできないものか」と問いかけています。そのうえで、「施設不足、政治の貧困とか言ってみたとて早急にこの問題は解決しそうもありません。今こそ私たちは、自分たちにできるかぎりの温かい手を障がい児にさしのべることが必要だと思う。健康に恵まれた私たちのなすべき社会的義務だと信じる」などと述べて、守る会への賛同を訴えています。
「遠足」が励ましに
設立直後の守る会は、当面の事業として、「会のPR活動」や「公的援助が受けられない家庭への経済的援助」などと合わせて「子どもたちを遠足やドライブに誘う」ことを計画に入れました。
その「遠足」の1回目が、皿井さんが創設した愛光園への「いもほり遠足」でした。1965年11月7日、障がいのある子11人と母親、ボランティア25人の計36人が参加しました。半年後には三ヶ根山ドライブなども計画され、地域を二つに分けた、レクリエーションへと活動は広がっていきました。
守る会の10周年誌には、1967(昭和42)年5月のレクリエーションに参加した会員で、碧南市の保健師だった多田代志子さんの次のような言葉が載っています。
〈この心身障がい児の多くは、四肢をはじめ、全身の運動や言葉の不自由から、社会集団から全くのけ者にされ、家の片隅で、母親の背に、あるいは乳母車や保持椅子、布団の中で1年のほとんどを過ごしていました。母親あるいはごく少数の人にのみ理解してもらって小さな生命を保っているのです…(中略)…きょうの楽しい日を反省して、家庭においても街角においても、あのようなうれしそうな表情を汲み取ってくださる人が一人でも多くなってほしいものだと思います〉
障がいのある子を連れての遠足やドライブは毎年続きました。重い知的障がいのある子の母親はこう書いています。
〈私は今、お詫びを申し上げずにはいられません。と申しますのは、最初守る会がご招待下さった時、健康な方たちに障がい児をもった親の悲しみが分かりっこない。裕福な人たちの慈善のように思っていました。ところが、2年3
年と過ぎても、会はつぶれるどころか、ますます活発に奉仕活動を続けられるのを知って、当時ひがんでいた私が恥ずかしくてなりません。障がい児をもたない人たちが心配していてくださる、力になってくださると思うと勇気が湧いてきます〉(10周年誌から)
遠足や訪問活動を続けることが、母親たちの励ましになっていたのです。
こうした初期の活動で記しておきたいことがいくつかあります。一つは、会員による施設見学会や勉強会も繰り返し開かれていることです。「重い障がいのある子どもたちのことをどう受け止め、何をすべきかをじっくり考える機会にしたい」と。例えば、Y君のいる「びわこ学園」などへも出かけ、「この子らを世の光に」の言葉で知られる糸賀一雄さんの講演会も開き、ボランティアの育成にも努めています。細かな記録はありませんが、障がいのある子の家に、内風呂をつくったことも記しておきます。大きくなった男の子を、銭湯では女湯に入れるしかなかった母親の悩みを聞き、気兼ねなく風呂に入ってもらえるようにと風呂桶を届けたのだそうです。
訪問時の対話がなければ気づけなかったことだし、内風呂をつくるという提案も、相手との信頼関係がなければ決してできなかったでしょう。
「一日保育」の始まり
遠足や訪問の積み重ねの一方、守る会が取り組んだのが、「刈谷手をつなぐ親の会」による通園施設設置運動への協力でした。同会の当時の副会長だった加藤和義さんは、守る会の設立時からの役員でもありました。就学猶予となっていた重度の心身障がい児の通園施設の設置を市に働きかけ、署名運動にも取り組んでいました。この署名運動を続けながら、手をつなぐ会と共同で始めたのが月に1
回の保育活動でした。
初回は1968(昭和43)年1月28日でした。「どの子も生まれてきてよかったという思いがかなえられるように願って始まったのが一日保育だった」と寿美ゑさんは後に記しています。知的障がいのある子の通園施設「しげはら学園」が開園する1973
(昭和48)年までは、決まった会場もなく、あちこちを借りて、保育道具を持って移動する、いわば「旅芸人風の保育」が続いたと振り返っています。刈谷市にある企業の従業員や学生たちでつくる「さざなみグループ」の若い仲間たちやボランティアの女性たちが、保育活動を支えてくれました。多い時には20人以上の子どもが参加しました。
1979(昭和54)年の養護学校義務化で重い障がいのある子どもも通学するようになると、一日保育に寄せる思いも変わってきたようです。ただ「障がいのあるとかないとかに関係なく、どの子も自然に親しみ、どんな小さないのちも、一本の木や草も大切に、共生して生きていける人間育ての場として引き継いでいってほしい」というのが、寿美ゑさんが引き継ぐ親たちに託した変わらぬ思いです。
「ひかりの家」開所
署名運動が実り、「しげはら学園」ができてからは、そこを拠点に、月3回の一日保育に取り組みました。「毎日集まれる場所がほしい」という声が生まれるのは自然な流れでした。
そんな時、地域の磯村浪さんのご厚意により、30坪の建物と200坪の土地を無償で借りられることになりました。
1973
年1月7日、「ひかりの家」が原崎町にオープンしました。糸賀一雄さんの言葉にあやかり、「ひかりの家」と名づけました。
当初は、障がいのある子どもたちの生活指導と療育相談の場として出発しました。子どもたちを二つのグループに分け、最初は週2日、やがて、週3日と保育日を増やしていきました。
ボランティアだけで始まった保育でしたが、「さざなみ」出身の長谷川由美さんが、大学を卒業して、専任指導員として市から派遣されるようになりました。やがて、送迎用の9
人乗りワゴン車も、刈谷衣浦ライオンズクラブからの寄付金やバザーの収益金で購入されました。1974(昭和49)年からは、心身障害児通園事業助成金の国庫補助を受けられるようになりました。
1980(昭和55)年4月、保健所を退職した寿美ゑさんがひかりの家の職員になり、母乳指導や食生活指導も手がけるようになりました。
1981(昭和56)年からは、月曜から金曜までの毎日の保育に切り替えるとともに、障がいのある子も、障がいのない子も共に育ち合う「混合保育」(原文のまま)をスタートさせました。
新しいひかりの家を建設するための陳情、請願署名の運動はすでに始まっていました。青年会議所の「愛の竹筒募金」が建設のための当初資金に組み込まれました。1981年の11月には「ひかりの家建設委員会」も発足。①行政の手の届かない部分を補っていく②学区の学校へ通うことのできない重度の子どもたちの通園の場とする③健常児との混合保育をする④大人になっていく障がい児たちの問題に対処する⑤緊急一時保育を行う―などが1回目の建設委員会で合意されました。
1983
(昭和58)年3月31日、現在の小山町で新しい「ひかりの家」の開所式が行われました。やわらかみがあって、あたたかな木の床の上での保育が始まりました。
その年の秋には、さくら・さくらんぼ保育園の斎藤公子園長(当時)を招いて講演会を開くなど、先進的な保育実践や混合保育に取り組むための試行錯誤が重ねられるようになりました。経験豊富な保育指導員がいなくなるなどの事態もあるなか、理念や目標、日課などの見直しや、保護者の要望を聞くことを重ね、保育目標などを確立してきました。
1994(平成6)年度の保育の状況について30周念誌から拾っておきます。
この年の入園児の内訳は、障がい児20人、健常児10人、デイサービス11人。これに対して、スタッフは、現場に12人(職員7、パート職員5)、事務3人(職員1、パート職員2)、その他4人(園長、非常勤講師ら)となっていました。
日課は、9時40分に登園し、15時降園の大枠は1986
(昭和61)年から続き、食事には、当時から1時間半をとっていました。掃除時間も設けられ、道具の使い方を学ぶとともに、手の力や足腰の力を育んできました。リズム運動やマッサージ、自然に親しむ散歩、五感を刺激する感覚運動や集団遊びなどがカリキュラムの中身となっていました。
(元朝日新聞記者 守る会50周年記念誌編集長 中沢一義)